【Aセット】中学校におけるラウンド制指導
〜技能統合を図り、英語が使える基礎力の育成のための指導の工夫〜
【全2巻】
商品番号 E125-A
販売価格12,000円(消費税込:13,200円)
[最大1,200ポイント進呈 ]
※送料については、こちらをご確認ください。
※商品の汚損・破損・故障等がなく、お客様のご都合での返品はお受けしておりませんので、ご注文の際には十分ご確認いただきますようお願い申し上げます。
※
DVDビデオ対応のプレーヤーでの再生を推奨しております。ゲーム機、車載DVDプレーヤー(カーナビ)等での動作は保証しておりません。

 ■授業・解説:杉本 義美(京都外国語大学 英米語学科 教授)
■授業・解説:杉本 義美(京都外国語大学 英米語学科 教授)
収録内容(Aセット 第1巻)
■中学校におけるラウンド制指導:概論
・ラウンド制指導について/ラウンド制指導のTeaching Procedure
■Oral interaction
指導者と生徒ができる限り英語のやり取りを通じて、
これから学習する教科書の内容に関係する背景知識や理解に
ヒントとなる情報を与える。
◎Oral interactionの進め方及び留意点と実際
■Round 1 (Listening)
Listeningによる概要を理解させるためにworksheetを配り、
First listeningの質問に答えさせ、ペアで答えを確認させる。
◎Listeningによる全体概要理解活動の進め方と実際
■Round 2 (Listening)
First Listeningでの概要理解を踏まえて、各part/paragraphにおける要点を理解させる活動で、
各part/paragraphごとに1つの要点に関する発問を与え、それに答えさせる。
◎Listeningによる各part/ paragraphの要点理解活動の進め方と実際
■Round 3 (Reading)
テキストを読んで、各part/ paragraphごとに、細部の内容を読み取る活動。
問われている内容を生徒に読ませて理解させ、生徒にただ黙読させるのではなく、
指導者が、テキストを読み聞かせ《音声を与え》ながら、テキストを読ませる。
◎Readingによる内容細部理解活動の進め方と実際
■Round 4 (Reading aloud 1)
概ね教科書の本文内容の理解が済んだので、音読練習を行う。
この段階(第1段階)の音読は、正しく文字を音声化でき、
意味を考えたリズム、イントネーションで音読できることを目指す。
◎初期段階での音読指導の進め方と実際
・Listen and repeat
・Read aloud & listen and repeat
・Japanese & read aloud
・Parallel reading aloud: read aloud at the same speed and rhythm & intonation
■Round 5 (Reading aloud & Second reading)
ある程度音読ができ内容が理解できた段階で、テキストには直接書いていないが、
学習者が読んだ内容から推測したり、予測したりすると解答できる発問を与える。
これにより、テキストをより深く理解できることを目指す。
◎推論発問について/Reading aloud & Second reading指導の実際
■Round 6 (Leveled reading aloud)
音読練習の第2段階で、英文を内在化する練習を行う音読練習。
音読シート(leveled reading aloud)を用いた練習で、
各レベルにおいてペアの一人がこのシートを見て英文を音読していく。
◎音読シート(leveled reading aloud)の説明・活用方法/Leveled reading aloud活動の実際
■Round 7 (Q & A in English)
教科書を閉じた状態で、先生の英語の質問に英語で答える活動。
教科書本文の意味内容が充分に理解できている前提で、
英語での質問に自分の言葉で英語で簡潔に答えることができるかを目的としている。
◎Q & A in English活動の実際
■Round 8 (Read & Look up)
英文を正確に内在化する目的で行う活動である。
1つのセンテンス単位でread & look upさせることを原則にするが、
複文の場合は、2つに分けてread & look upさせる等、
生徒の学力レベルに応じて、1度にreadさせる量を調整する。
◎Read & Look up活動の実際
■Round 9 (T or F Questions)
教科書閉本で行うまとめの活動で、output活動に結び付ける構成になっている。
与える英文は誤文を多くし、これまでの活動で理解したテキストの
本文内容に合わせて、正しい文になるように書き換えさせる活動。
◎T or F Questions について/活動の実際
■Round 10 (Summary)
T or F Questions活動で作った正しい英文をつなげれば、
その本文の要約《サマリー》がある程度できるようになる。
勿論この段階で、生徒が必要な情報等を足すこともできる。
◎サマリー活動について
■Round 11 (Q & A in English in pairs)
まとめの生徒同士のoutput活動で、生徒同士が英語で質問して、答えあう。
この段階では、内容理解、音読、簡単なoutput活動が終わっていることが前提である。
◎生徒同士の英問英答活動について/Q & A in English in pairs活動の実際
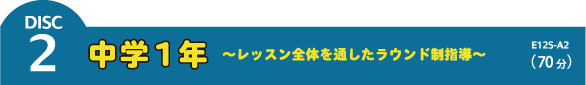
収録内容(Aセット 第2巻)
*各ラウンドの目的・活動内容は中学3年(E125-A1)のものをご参照ください
■Oral interaction
■Round1(Listening)Listeningによる全体概要理解
■Round2(Listening)Listeningによる各partの要点理解
■Round3(Reading)内容細部理解
■Round4(Reading aloud 1)初期段階での音読指導
■Round5(Reading aloud & Second reading)推論発問
■Round6(Leveled reading aloud)
■Round7(T or F Questions)/Round8(Summary)
■Round9(Reproduction of the story)
黒板にキーワードをいくつか提示したり、教科書のpicturesを提示してそれらを使って、
テキストの内容を自分の英語で言わせる活動
<ラウンド制指導の留意点>
1.第二言語習得の認知プロセスが基本:
内容理解(概要→要点→細部)活動、内在化(音読)活動、output活動へと
4技能を統合した活動をラウンドに組み込むこと。
2.生徒同士が考える場を与えること:
指導者は安易に答を与えないこと(ヒントを与えること)。教材の工夫。
3.常に音声を生徒に与えること:
指導者が常に英語で正しいinputを与え続けること。
4.リズムとテンポが大切:
ただ読んで解答させるのでなく、生徒の集中力を考えて時間を切って
各ラウンドに取り組ませること。
5.1時間ですべてのラウンドが終了しない:
前時の復習を入れながら、新たなラウンドに進むこと。
2017.8